一歩先んじた情報収集が勝ち残り企業の条件。
機先を制する経営情報源として「ワンポイント動画」をぜひご活用下さい。
パートナーズプロジェクト税理士法人のワンポイント動画一覧
絞り込みをする
中小企業も対象!パートナーシップ構築宣言の概要とメリット
経済産業省が推進する「パートナーシップ構築宣言」。取引の適正化やサプライチェーン全体の共存共栄を目指すこの制度、補助金や税制優遇といったメリットも豊富です。中小企業の参加も増加中。
今こそ自社の信頼性と連携力を高めるチャンスです。

100億宣言ポータルサイト公開
100億宣言ポータルサイトがオープンしました。
中小企業の皆様が飛躍的成長を遂げるために、自ら、「売上高100億円」という野心的な目標を目指し、実現に向けた取組を行っていくことを宣言するものです。
それに伴う補助金や税制優遇も用意されています。
売上10億を越えている会社は大型投資を計画している場合はメリット大! 5/8スタートです。
100億宣言ポータルサイト→https://growth-100-oku.smrj.go.jp/

モグラ叩きから考える経営課題への対処法
中小企業の経営者の皆様へ、経営課題の対処法についての解説動画をお届けします。
経営者は求人難や昇給、資金不足など多くの課題に直面しています。
これに対処するためには、まず重要な課題から取り組むことが基本です。

日本人の成人力は世界トップクラス
今回は、日本人の成人力の高さについてお話しします。
近年、日本の国際ランキングは低下傾向にありますが、成人力ランキングでは、数的思考力で2位、問題解決能力で1位を獲得しました。特に、変化に適応した問題解決力が評価されています。

人はどこにいる?
求人市場では30代・40代男性の応募が少なく、人手不足が本格化しています。
厚生労働省の調査によると、この世代の9割以上がすでに正規雇用で働いており、新規採用は困難です。
一方、30代・40代女性は労働参加率が低く、非正規雇用が多い点に着目すると、転職や復職支援で採用拡大が期待されます。

あなたの業界の利益率は?業種別利益率を徹底解説!
「どの業界が儲かるの?」そんな疑問にお答えします。
本動画では、TKCの膨大なデータを基に、様々な業種の利益率を徹底比較!売上高に対する経常利益率だけでなく、総資産に対する経常利益率も分析し、意外な事実が明らかに!
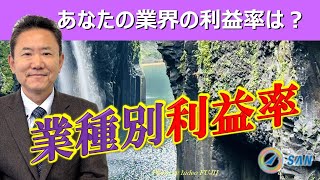
中小企業の平均年収/規模別・年齢別
この動画は、中小企業の年収について、規模別や年齢別に詳しく解説しています。
従業員数や資本金の異なる企業が、どのように年収に影響を与えるかをグラフで示し、特に50代にピークが来る傾向が見られます。
従業員10名未満の小規模企業では年収が低く、年齢が上がるにつれて増える一方、30名以上の企業では年収がさらに高いことが分かります。また、個人事業と法人を比較すると、法人の平均年収が1.5倍高いという差があり、企業規模に応じた年収の違いも解説しています。
この情報は、中小企業の経営者が賃金設定や給与交渉の際に参考にできる内容となっています。動画は賃上げの継続に触れ、今後の動向についても関連付けて解説しています。

中小企業の平均年収はどのくらい?令和5年版
この動画では、中小企業の年収について、民間給与実態統計調査を基に詳しく解説されています。2023年の総平均年収は460万円で、47歳が平均年齢、勤続年数は12.5年でした。
正規・非正規別の年収格差は大きく、正規社員とそれ以外では倍以上の違いがあることがわかります。また、企業規模が大きくなるほど年収が増加し、年齢や勤続年数が若干短くなる傾向が見られます。女性の年収は男性に比べて伸びが鈍く、その原因として非正規雇用の増加や出産・育児によるキャリア中断が影響しています。現在の賃金上昇率は期待を下回り、賃金引き上げは今後も続く見込みです。
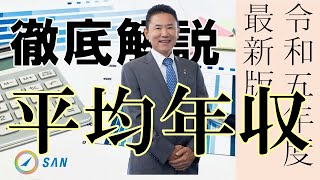
若者の採用・定着をサポート<ユースエール認定>_
ユースエール認定制度は、若者が働きやすく成長できる企業を国が認定する制度です。厚生労働大臣が、若者の採用と定着を促進するために企業を認定し、ハローワークでのPRや専用面接会への参加などのメリットがあります。主な基準は、中小企業であること、労働法違反がないこと、新卒者の内定取り消しがないことなどが挙げられます。離職率や残業時間、育児休暇の取得率などの基準を満たすことで、認定を受けることができます。

事業承継の新たなステージ~成長のチャンスと後継者育成の戦略
事業承継は新たなステージに入り、成長のきっかけとして重要視されています。
後継者が見つからない場合、自分の分身を探すのではなく、後継者の得意分野に合わせた一部承継や他者に任せることも視野に入れるべきです。
また、事業承継を機に事業再構築に取り組む企業も増えており、組織全体の活性化が見られます。
国は事業承継やM&Aを通じて生産性向上を支援し、経営者の自己改革を求めています。
後継者育成と「右腕人材」「変革人材」の採用・育成が今後の鍵となります。



 お問い合わせ
お問い合わせ
